静電気試験の手順や条件とは?関連用語やESD発生器についても解説!
2025年5月10日更新
この記事を書いた人

大手メーカー「コマツ」、「オムロン」などで7年間、アナログ回路エンジニアとして設計・評価業務に従事。
ECU、PLCなどのエレキ開発経験を多数持つほか、機械商社での就労経験も有する。
株式会社アイズ運営の機電系フリーランスエンジニア求人情報「FREEAID」専属ライターとして、
機電分野の知識と実務経験を活かし、専門性の高い記事執筆を行っている。
乾燥した冬場などに発生する、静電気による放電現象。人間にとっては僅かな痛みを伴う身近な現象に過ぎませんが、実は電子機器に大きな影響を及ぼすため、製品においては静電気への耐性を確認する必要があります。今回はそんな電子機器の静電気耐性を確かめる静電気試験について、国際規格をベースに規定されたJIS C 61000-4-2の内容を中心に解説していきます。
静電気の定義と試験が必要な理由
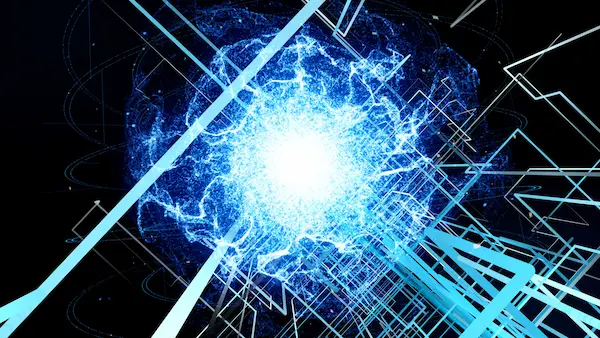
そもそも静電気とは、名前の通り電気的な流れ(電流)がなく物質に帯電した電荷のことです。帯電する電荷量が増加したり、近くに導電性の物質が接近すると、我々が日常的に経験する放電現象を引き起こします。一般的に静電気には数千から数万ボルトオーダーの電荷量を持っており、電気抵抗値が大きい人体においてはほとんど影響を及ぼしません。
一方で、数mVオーダーの電圧を扱う電子回路には誤作動や故障を招く恐れがあるうえ、可燃性ガスを扱う工場などでは静電気が爆発や火災事故を招く着火源にもなりえます。そのため、電子機器には静電気放電の影響を受けたり、発生させない能力が求められています。
静電気試験を理解するための略語
静電気試験の規格では、様々な略語が使用されているため、それらについても覚えておきましょう。まず、静電気によって引き起こされる放電現象は「ESD」と呼ばれ、静電気試験によってESDの被害を受ける電子機器や電気機器は「EUT」と呼ばれます。また静電気試験の際に導電性物質を模擬する目的でEUTの近くに置く金属板や金属面のうち、水平結合板を「HCP」、垂直結合板を「VCP」と呼びます。これらの用語はJIS C 61000-4-2の中で頻繁に登場するため、しっかりと覚えておきましょう。
静電気試験の種類

静電気試験は試験方法の違いによって2種類に分かれています。それぞれの試験方法について解説していきましょう。
直接放電試験
EUTに対して直接ESDを印加し、耐久性を確かめる試験を「直接放電試験」と呼びます。放電方式は接触放電法と気中放電法の2種類に分かれており、接触放電法による試験では、先の尖った鋭利な電極を金属筐体部などEUTの導電性部分に接触させた状態で、高電圧のESDを印加して行います。
これに対し気中放電法による試験では、充電状態にした先の丸い電極を、プラスチック筐体などEUTの非導電性部分へ触れるまで素早く近付けて試験を行います。どちらの試験でも電極は可能な限り垂直にEUTに当て、試験レベルに応じた電圧のESDを10回以上印加するのが基本で、可能なかぎり接触放電試験を優先して実施することも要求されています。
間接放電試験
間接放電試験は、EUTに直接ESDを印加するのではなく、EUTの近くに置いたHCPやVCPにESDを直接印加することで、EUTに間接的に静電気被害を与える試験です。地面と水平に配置するHCPを使用する場合、EUTの正面がHCPの端面から0.1mの箇所となるよう機器を配置し、HCPの端面に電極を当ててESDを印加します。
VCPを使用する場合はEUTから0.1m離した箇所に平行になるようVCPを配置し、VCPの端面に電極を当ててESDを印加します。VCPは卓上機器と床置機器の両方に使用できる一方で、HCPは卓上機器にしか使用できません。
静電気試験に必須のESD発生器とは
静電気試験ではESDガンやESDシミュレータとも呼ばれるESD発生器が欠かせません。ESD発生器の内部には放電経路のインピーダンスを模した抵抗や人体の静電容量を模したコンデンサがあり、充電動作と放電動作を切り替えるスイッチやESDのエネルギー生み出す直流電源なども内蔵されています。
JIS規格ではESD発生器が出力可能な電圧範囲が定められており、接触放電モードであれば公称値は1kVから8kV、気中放電モードであれば公称値は2kVから15kVの範囲内であることとされています。他にも出力電圧の精度が5%以下であることや、保持時間が5秒以上であること、正負両方の極性の電圧が出力できることなども規定されており、放電操作モードも1秒以上の間隔を持った単発放電でなくてはなりません。
静電気試験を行う条件・手順
静電気放電による影響を正しく測定するには、静電気試験を行う環境や手順にも十分な配慮が必要です。
静電気試験を行う部屋の環境条件
ESDによる影響はEUTを使用する環境によって左右されるため、静電気試験は標準的な環境条件下で行うことが義務付けられています。具体的には試験室の室温が15℃から35℃で湿度は30%から60%、気圧が86kPaから106kPaまでの範囲内とされ、EUTが特定の気象条件下で使用される機器である場合のみ、これ以外の環境条件で試験しても良いとされています。また試験室の電磁環境についても、試験結果に影響を与えずEUTが正常に動作することが保証された環境でなくてはなりません。
静電気試験のレベル
静電気試験は試験電圧によって5段階のレベルに分けられ、レベルによって放電ピーク電流や特定の時間における電流値などが規定されています。例としてレベル1であれば2kV、レベル2であれば4kVの試験電圧が規定されており、レベル3以上では直接放電試験と間接放電試験で規定されている試験電圧が異なるものの、同じレベルであれば同等の厳しさとして扱われます。また装置の仕様書によって特別に規定された場合に限り、これらのレベルとは異なる任意の電圧を試験電圧として選択することもできます。
静電気試験の手順
環境の整った試験室が用意できたら、EUTの動作条件や試験のレベル、ESDを印加する場所や回数などを定めた試験計画を立案して試験に臨みます。EUTと試験機器のセットアップはEUTの種類によって異なるものの、いずれの機器にも共通する準備として、一定以上の厚みや大きさを持った金属製シートを基準グラウンド面として用意しなくてはなりません。試験計画に基づいて試験を実施したら、試験に使用した機器や環境条件など、試験を再現する上で必要な情報を全て盛り込んだ報告書を作成し、試験は完了です。
試験における注意点
静電気試験を行う際は、外乱による試験結果の揺らぎを抑えるため、EUTを試験室の環境に十分馴染ませてから実施する必要があります。また直接放電試験を採用する場合であれば、通常の使用において人間が接触可能な点や面のみにESDを印加することと規定されており、機器の設置後に触れない箇所や点検時にのみ触る箇所にはESDを印加する必要はありません。
さらに自然に電荷が除電されない非接地系の装置に直接放電試験を実施する場合、自然に帯電した電荷をあらかじめ除電してからESDを印加する必要があり、またESDの印加が終了する度に金属部品の除電も行う必要があります。
まとめ
今回は電子・電気機器の静電気耐性を確かめる静電気試験について、試験の種類や具体的な手順などを網羅的に解説してきました。静電気放電は身近な現象である一方で、試験時には予想以上の厳密性が求められることに驚いた方も多いのではないでしょうか。実際の規定ではセットアップなどについて、今回紹介した以上に細かく規定されているため、気になる人は詳しく調べてみてはいかがでしょうか。
当サイトFREE AIDは、機電系を始めとしたエンジニアのフリーランス専門求人を扱っています。
→機電系フリーランスエンジニア求人はこちら
また、フリーランスエンジニアとして働きたい方に合った案件探しや専門アドバイザーの活動サポートも無料で行っています。
→フリーランス無料支援に興味がある方はこちら

この記事の運営元:株式会社アイズ
「アウトソーシング」「ビジネスソリューション」「エンジニアリング」「ファクトリーオートメーション」の4つの事業を柱に、製造業やICT分野の課題解決を力強くサポートします。
フリーランスの機電系エンジニア求人情報サイト「FREE AID」を運営しています。
 機電系求人はこちら
機電系求人はこちら
設計技術者(樹脂、金属部品)
- 単価
40~50万円
- 職種
- 機械設計
- 詳細を見る
FPGAの設計開発:電気電子設計
- 単価
70~80万円
- 職種
- 電気電子設計
- スキル
- ・FPGA論理設計、RTLコーディング、論理検証環境構築、論理検証・RTLコード:VHDL・論理検証ツール:Siemens製Questa/ModelSIM
- 地域
- 東京
- ポイント
- #高単価
- 詳細を見る
UI画面の設計業務:電気電子設計
- 単価
64〜万円
- 職種
- 開発
- 電気電子設計
- スキル
- 必要スキル: ・電源回路は複数回経験し、設計動作確認など、一人でもある程度やるべきことが分かる。 ・数十頁のデータシートを読み、要求仕様(タイミング/電圧など)が理解できる ・その他左記の回路の種類の中で、回路設計の実務経験が1回以上ある。 ・回路修正ができる(半田付け、ジャンパー処理)
- 地域
- 関西
- ポイント
- #業務委託#駅近
- 詳細を見る
【急募】工作機械メーカーにおける自社製品の制御設計
- 単価
40~50万円
- 職種
- 電気電子設計
- スキル
- 基本的なPCスキル産業用機械・装置の電気設計経験
- 地域
- 山梨県
- ポイント
- #業務委託
- 詳細を見る





