遷移金属とは?性質・種類・典型元素との違いなど網羅的に解説!
2025年5月10日更新
この記事を書いた人

大手メーカー「コマツ」、「オムロン」などで7年間、アナログ回路エンジニアとして設計・評価業務に従事。
ECU、PLCなどのエレキ開発経験を多数持つほか、機械商社での就労経験も有する。
株式会社アイズ運営の機電系フリーランスエンジニア求人情報「FREEAID」専属ライターとして、
機電分野の知識と実務経験を活かし、専門性の高い記事執筆を行っている。
世の中に存在する元素の中には、遷移金属と呼ばれる金属があるのをご存じでしょうか。実は一般的に思い浮かべる金属のほとんどが遷移金属に該当するのですが、具体的な定義や性質を知らない人も多いことでしょう。そこで今回は、遷移金属に関する基本的な内容について解説します。
遷移金属とは

世の中に存在する元素のうち、第1族と第2族、および第12族以上に存在する元素を典型元素と呼ぶのに対し、第3族から第11族の間に存在する元素を遷移元素と呼びます。遷移元素は全て金属元素であるため、遷移金属とも呼ばれます。また、亜鉛や水銀などの第12族の元素は、場合によって遷移元素に分類されることもあります。
典型元素と遷移金属の違い
あらゆる原子は、陽子と中性子から構成される原子核と、原子核を囲う電子殻上を周回する電子によって構成されます。1つの電子殻に入ることができる電子の数は2n2(nは主量子数)個までと決まっており、例として原子核に最も近いK殻であれば2個まで、次に近いL殻であれば8個までとなります。
ここで、典型元素では内側の電子殻から外側の電子殻に向かって電子が入っていくのに対し、遷移金属では内側の電子殻が全て埋まっていないにも関わらず、外側の電子殻に電子が入ります。電子の位置が異なることから、結果的に典型元素とは異なる化学的性質を示すようになります。
遷移金属の種類
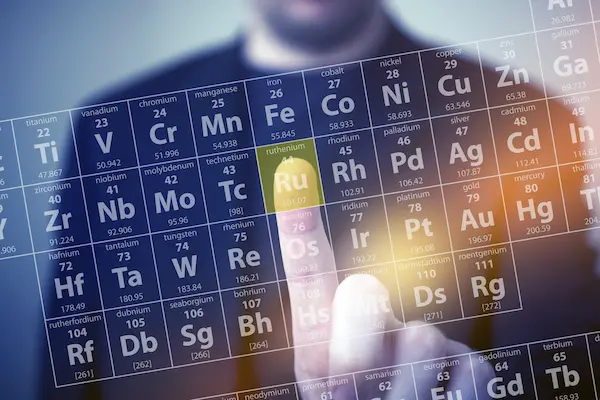
遷移金属は周期表における周期によって、第1遷移金属(第4周期)から第4遷移金属(第7周期)の4種類に分けられます。それぞれの種類ごとでどのような遷移元素が分類されているかを紹介します。
第1遷移金属・第2遷移金属
第1遷移金属は3d軌道に電子が埋まっていくため、3d遷移元素と呼ばれることもあり、具体的な種類としては鉄や銅、チタン、コバルト、マンガン、ニッケルなどがあります。また、4d遷移金属とも呼ばれる第2遷移金属に該当するのは、銀やモリブデン、イットリウム、ジルコニウム、パラジウムなどです。
第3遷移金属・第4遷移金属
第3遷移金属と第4遷移金属は、d軌道に電子が入っていくdブロック元素に加え、さらに内側のf軌道に電子が入っていくfブロック元素に分けられます。第3遷移金属のdブロック元素には金や白金、タンタル、タングステンなどが該当し、fブロック元素に該当するのはランタンからルテチウムまでの15種類の元素です。
また、第4遷移金属におけるdブロック元素には、レントゲニウムやラザフォージウム、ボーリウムなどが該当し、fブロック元素にはアクチノイドからローレンシウムまでの15種類が該当します。なお同じ周期のfブロック元素はいずれも似通った性質を持つことから、第3遷移金属のfブロック元素はランタノイド、第4遷移金属のfブロック元素はアクチノイドと一括りに呼ぶことが多いです。
遷移金属が持つ代表的な性質
遷移金属は特徴的な性質がいくつかあります。順番に解説していくので、しっかりと覚えておきましょう。
密度が大きく融点が高い
遷移金属には密度が大きく融点が高いという性質があり、我々が一般的に思い浮かべる金属のイメージに合致しています。実際、密度に関して言えばスカンジウムを除く全ての遷移金属が比重4[g/cm3]を超えているため、重金属に分類されます。
また融点についても1000℃を超える金属が多く、遷移金属の代表例である鉄は1536℃、銅は1085℃です。第12族は遷移金属と典型元素どちらにも分類されると説明しましたが、水銀の融点が-39℃、亜鉛の融点が420℃と低いことからも、遷移金属とは異なる性質を持っていることが分かるでしょう。
1つの元素が複数の酸化数を持つ
遷移金属には、1つの元素が複数の酸化数を持つ性質もあります。例として、鉄であればFe2+とFe3+、Fe6+などのイオンがあり、化合物も酸化数が2のFeO(酸化鉄(Ⅱ))や酸化数が3のFe2O3(酸化鉄(Ⅲ))などが存在します。他にも銅であればCu+やCu2+、Cu3+などのイオンがあり、化合物にはCu2O(酸化銅(Ⅰ))や、CuO(酸化銅(Ⅱ))などがあります。
またマンガンにはMn2+やMn3+、Mn4+、Mn6+、Mn7+など酸化数が異なるイオンが複数あり、化合物もMnO2(酸化マンガン(Ⅳ))や、KMnO4(過マンガン酸カリウム)など様々な酸化数を持つ種類が存在します。
族が異なる元素同士であっても似た特徴を持つ
周期表において同じ族に分類される元素(通称、同族元素)は、原子構造における最外殻電子の数が同じため、似たような性質を示すことで知られています。例えば水素を除く第1族の金属元素はアルカリ金属と呼ばれ、密度が小さい上に融点も低く、柔らかいという性質があります。
一方の遷移金属では、最外殻電子のうち反応に使われる価電子の数が同じ元素が多く、族が異なる元素であっても性質が似通ったものが多いです。実際、鉄族元素と呼ばれる鉄とコバルト、ニッケルは、いずれも常温で強い強磁性を持っており、白金族元素と呼ばれる白金やイリジウムなども、水と反応せず酸や塩基にも侵されにくい特徴があります。
イオンや化合物に色がある
遷移金属に該当する元素は、イオンや化合物に色がついている物が多いのも特徴です。イオンであればCu2+が青色、Fe2+が淡緑色、Fe3+が黄褐色、ni2+やCr3+が緑色、Mn2+が淡赤色といったように、元素の種類や酸化数によって多彩な色となります。また遷移元素からなる化合物の色は、d軌道の電子数やイオンと結合する配位子の配置や構造によって異なり、Cu2O(酸化銅(Ⅰ))であれば赤色、CuO(酸化銅(Ⅱ))であれば黒色となります。
触媒として作用するものが多い
遷移金属には触媒として作用するものが多く、特定のガスを生成する場合など工業用途で使用されることがあります。例えば過酸化水素水から酸素を生成する場合であれば、遷移金属のマンガンが含まれた化合物、MnO2(酸化マンガン(Ⅳ))を触媒として使用します。また硫酸を工業的に製造する過程においては、遷移金属に該当するバナジウムを利用して、V2O5(五酸化バナジウム)を触媒とした接触法を用いるのが一般的です。
最近新発見された遷移金属もある?
2024年末には東京都立大学や北海道大学、広島大学、ローマ大学サピエンツァ校らの研究グループが、遷移金属ジルコナイドの合成に成功したと発表されています。遷移金属ジルコナイドには、同じく遷移金属である鉄とニッケル、およびジルコニウムが含まれており、同グループが磁化率や電気抵抗率、比熱などを調べて超電導性質を評価したところ、極低温下で電気抵抗値がゼロとなり、超電導体としての性質も発現したと発表されています。最新の動向を知りたい方は詳しく調べてみては如何でしょうか。
まとめ
今回は数多く存在する元素の中で、遷移金属とも呼ばれる遷移元素について解説してきました。鉄や銅、金など、身の回りに存在する金属のほとんどが遷移金属に該当することが分かったのではないでしょうか。水銀や亜鉛のように遷移金属と典型元素の両方に分類される族もあるので、性質などをしっかり理解して覚えるようにしましょう。
当サイトFREE AIDは、機電系を始めとしたエンジニアのフリーランス専門求人を扱っています。
→機電系フリーランスエンジニア求人はこちら
また、フリーランスエンジニアとして働きたい方に合った案件探しや専門アドバイザーの活動サポートも無料で行っています。
→フリーランス無料支援に興味がある方はこちら

この記事の運営元:株式会社アイズ
「アウトソーシング」「ビジネスソリューション」「エンジニアリング」「ファクトリーオートメーション」の4つの事業を柱に、製造業やICT分野の課題解決を力強くサポートします。
フリーランスの機電系エンジニア求人情報サイト「FREE AID」を運営しています。
 機電系求人はこちら
機電系求人はこちら
設計技術者(樹脂、金属部品)
- 単価
40~50万円
- 職種
- 機械設計
- 詳細を見る
FPGAの設計開発:電気電子設計
- 単価
70~80万円
- 職種
- 電気電子設計
- スキル
- ・FPGA論理設計、RTLコーディング、論理検証環境構築、論理検証・RTLコード:VHDL・論理検証ツール:Siemens製Questa/ModelSIM
- 地域
- 東京
- ポイント
- #高単価
- 詳細を見る
UI画面の設計業務:電気電子設計
- 単価
64〜万円
- 職種
- 開発
- 電気電子設計
- スキル
- 必要スキル: ・電源回路は複数回経験し、設計動作確認など、一人でもある程度やるべきことが分かる。 ・数十頁のデータシートを読み、要求仕様(タイミング/電圧など)が理解できる ・その他左記の回路の種類の中で、回路設計の実務経験が1回以上ある。 ・回路修正ができる(半田付け、ジャンパー処理)
- 地域
- 関西
- ポイント
- #業務委託#駅近
- 詳細を見る
【急募】工作機械メーカーにおける自社製品の制御設計
- 単価
40~50万円
- 職種
- 電気電子設計
- スキル
- 基本的なPCスキル産業用機械・装置の電気設計経験
- 地域
- 山梨県
- ポイント
- #業務委託
- 詳細を見る





