高調波電流とは?影響・原因・対策・制限値について網羅的に解説
2025年5月10日更新
この記事を書いた人

大手メーカー「コマツ」、「オムロン」などで7年間、アナログ回路エンジニアとして設計・評価業務に従事。
ECU、PLCなどのエレキ開発経験を多数持つほか、機械商社での就労経験も有する。
株式会社アイズ運営の機電系フリーランスエンジニア求人情報「FREEAID」専属ライターとして、
機電分野の知識と実務経験を活かし、専門性の高い記事執筆を行っている。
送配電系統において発生する高調波電流をご存知でしょうか。今回は送配電系統における問題として扱われる高調波電流について、具体的な影響や発生原因、対策、制限値などを網羅的に解説します。
高調波電流とは
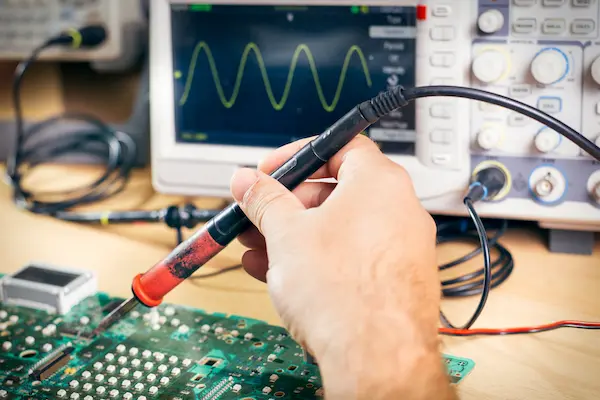
JIS規格によると、高調波とは通常使用する周波数(50Hzや60Hz)の信号に対して正数倍の周波数を持つ正弦波形と定義されており、高調波電流も同様の周波数を持つ電流信号のことです。使用する信号の周波数が50Hzであれば、100Hzの信号が第2次高調波、150Hzの信号が第3次高調波となり、一般的には第40次までを高調波信号として扱います。発電所で作られた電源は綺麗な交流波形をしていますが、様々な電子機器に入ることで高調波が発生し、電源波形がゆがむこととなります。
なお実際の計算では偶数次の高調波電流はほとんど出てこないので、一般的に高調波電流といえば第3次や第5次など奇数次の信号であることを覚えておきましょう。また高調波電流の類似用語として高周波電流もありますが、高周波電流は2kHzを超える高調波電流を指す用語のため、間違えないようにしましょう。
高調波電流の影響とは
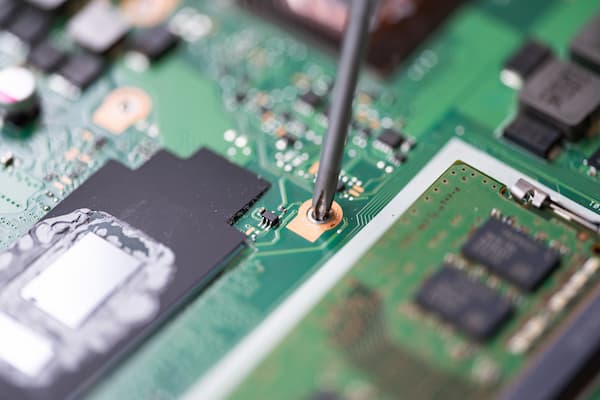
高調波電流は基本周波数の波形を歪ませることで電気の質を低下させ、機器の動作不良や故障などを引き起こします。家電製品であれば、テレビやラジオの映像や音声が乱れたり、電子レンジや洗濯機などの家電製品が動かないといった不具合を引き起こします。また電力設備であれば、モータの異音や振動、リアクトルの過熱や焼損、ヒューズの溶断などを引き起こし、最悪の場合には電力系統全体に悪影響を及ぼします。
高調波電流は力率コンデンサに与える影響が特に大きく、振動やうなり、異常過熱による焼損などを引き起こします。力率コンデンサとは、変圧器やモータなどのインダクタンス成分が支配的になる電力系統において、遅れ力率を改善する目的で設置されるコンデンサのことです。
一般的にコンデンサには、周波数が高くなるほどインピーダンスが低くなる性質があるため、周波数が高い高次の高調波電流の影響を受けやすく、場合によっては系統に存在するインダクタンスと共振現象を起こすことで、高調波電流の発生を促進する恐れがあります。
高調波電流が起きる原因
高調波電流はダイオードやサイリスタ、トライアックなどの非線形負荷が原因で発生します。非線形負荷とはスイッチングのタイミングや負荷の特性により、流れる電流波形が綺麗な正弦波とならない負荷のことで、具体例としてはコンデンサインプット型の整流回路やインバータ、アーク炉などが挙げられます。ちなみに抵抗やインダクタンスなど、負荷電流波形が綺麗な正弦波となる負荷は線形負荷と呼ばれ、線形負荷のみの回路では高調波電流は発生しません。
代表的な高調波電流の対策

続いて高調波電流を抑制する代表的な対策について解説していきます。
パッシブフィルタ
高調波電流の対策として1つ目に挙げられるのは、チョークコイルなどに代表されるパッシブフィルタです。利点として回路構造が簡単で電力損失も少ない点が挙げられるものの、入力電圧が狭くなったり、部品が大きくて重いなどのデメリットもあります。
チョークコイルの使用により、スイッチングのタイミング等に瞬間的に流れる高調波電流をならすことで、電流波形を正弦波形に近づけるイメージです。なお、チョークコイル以外に抵抗素子やトランスを使用するパッシブフィルタもあります。
アクティブフィルタ
2つ目に挙げられる対策はアクティブフィルタの設置です。アクティブフィルタは名前の通り能動的に機能するフィルタであり、負荷の運転状況を常時監視しながら、発生した高調波電流と同じ大きさで逆位相の電流を流すことで高調波電流を打ち消します。高調波電流の抑制効果が非常に高い対策方法として知られ、複数の高調波電流を同時に打ち消すことができるため、他の対策を施してもなお高調波電流が抑制されない場合に使用される事が多いです。
リアクトルを内蔵した進相コンデンサ
進相コンデンサが高調波電流の影響を受けやすいことを逆手に取り、対策としてリアクトル内蔵型の進相コンデンサを設置する場合もあります。直列にリアクトルを接続することで進相コンデンサ回路が誘導性となり、負荷回路に流れる高調波電流を抑制できるのです。
なお、進相コンデンサが高調波電流から受ける影響は直列リアクトルの有無によって大きく左右されるため、該当するJIS規格が1998年に改正されてからは、原則として進相コンデンサには直列リアクトルの設置が要求されています。
高調波電流に対する規制

高調波電流は系統に様々な悪影響を及ぼすため、JIS規格やIEC規格などでは高調波電流の値に制限を設けています。ここでは、それぞれのクラスに該当する機器やクラス毎の電流制限値について解説していきましょう。なお、実際には条件によって多くの規定があるため、気になる人はネットなどで詳しく調べてみることをオススメします。
JIS規格における4つのクラスについて
JIS規格では、電気機器をクラスAからクラスDまでの4種類に分類し、それぞれのクラスに対して高調波電流の制限値を設けています。クラスAに該当するのはクラスB、C、Dのいずれにも該当しない機器で、真空掃除機や高圧洗浄機、オーディオ機器、平衡三相機器などが該当します。
クラスBには手持ち形電動工具と専門家用ではないアーク溶接機器が該当し、クラスCにはランプや照明器具、広告用の電飾サインといった照明機器が該当します。またクラスDに該当するのは、JIS規格で定める方法に則って測定した有効入力電力値が、600W以下である機器のうち、パソコンやモニタ、テレビ、インバータ制御の圧縮機を内蔵した冷蔵庫などです。
クラスA・クラスBに対する制限
クラスAの機器における高調波電流は、対象となる高調波電流の次数と定格電圧によって定まります。例えば定格電圧が230Vの機器の第3次高調波電流は2.3A以下までとされ、第5次高調波電流は1.14A以下、第7次高調波電流は0.77A以下までとされています。定格電圧が異なる場合の電流制限値は、基準となる230Vを定格電圧で除した値を乗算することで求められ、三相機器に限っては基準電圧が400Vとなります。
また有効入力電力が600Wを超えるエアコンの電流制限値の算出には、専用の計算式を使わなくてはなりません。そしてクラスBの機器における電流制限値は、クラスAの機器の1.5倍以下とされています。
クラスC・クラスDに対する制限
クラスCの機器に対する高調波電流制限値は機器の仕様によって異なります。例えば定格有効入力電力が25 Wを超える機器のうち、白熱電球を位相制御調光器で制御する照明器具に限っては、クラスAの機器に対する制限値を適用します。また定格有効入力電力が25Wを超える機器のうち上記以外の照明器具については、照明器具の入力電流に対する比率で制限値が定義されており、第5次高調波であれば10%以下、第7次高調波なら7%です。
そしてクラスDの機器については最大許容高調波電流値だけでなく、電力比例限度値も定義されており、定格電圧230Vの機器であれば第3次高調波電流が2.3A以下、電力比例限度値が3.4mA/Wとなります。
まとめ
今回は電力系統において問題になる高調波電流について、言葉の定義から制限値まで網羅的に解説してきました。高調波電流は一般家庭にも悪影響を及ぼす現象であるので、興味のある方は身の回りの機器がどんな影響を受けるかを調べてみるのも良いかもしれません。
フリーランス×機電系エンジニア!高単価求人はこちら ▶
この記事の運営元:株式会社アイズ
「アウトソーシング」「ビジネスソリューション」「エンジニアリング」「ファクトリーオートメーション」の4つの事業を柱に、製造業やICT分野の課題解決を力強くサポートします。
フリーランスの機電系エンジニア求人情報サイト「FREE AID」を運営しています。
 機電系求人はこちら
機電系求人はこちら
設計技術者(樹脂、金属部品)
- 単価
40~50万円
- 職種
- 機械設計
- 詳細を見る
FPGAの設計開発:電気電子設計
- 単価
70~80万円
- 職種
- 電気電子設計
- スキル
- ・FPGA論理設計、RTLコーディング、論理検証環境構築、論理検証・RTLコード:VHDL・論理検証ツール:Siemens製Questa/ModelSIM
- 地域
- 東京
- ポイント
- #高単価
- 詳細を見る
UI画面の設計業務:電気電子設計
- 単価
64〜万円
- 職種
- 開発
- 電気電子設計
- スキル
- 必要スキル: ・電源回路は複数回経験し、設計動作確認など、一人でもある程度やるべきことが分かる。 ・数十頁のデータシートを読み、要求仕様(タイミング/電圧など)が理解できる ・その他左記の回路の種類の中で、回路設計の実務経験が1回以上ある。 ・回路修正ができる(半田付け、ジャンパー処理)
- 地域
- 関西
- ポイント
- #業務委託#駅近
- 詳細を見る
【急募】工作機械メーカーにおける自社製品の制御設計
- 単価
40~50万円
- 職種
- 電気電子設計
- スキル
- 基本的なPCスキル産業用機械・装置の電気設計経験
- 地域
- 山梨県
- ポイント
- #業務委託
- 詳細を見る





