高性能メモリ「HBM」とは?構造・特徴・製造技術などを分かりやすく解説
2025年4月27日更新
この記事を書いた人

大手メーカー「コマツ」、「オムロン」などで7年間、アナログ回路エンジニアとして設計・評価業務に従事。
ECU、PLCなどのエレキ開発経験を多数持つほか、機械商社での就労経験も有する。
株式会社アイズ運営の機電系フリーランスエンジニア求人情報「FREEAID」専属ライターとして、
機電分野の知識と実務経験を活かし、専門性の高い記事執筆を行っている。
従来のメモリより大幅に優れた性能を持ち、AIなどの最先端分野での活躍が期待されているHBMをご存知でしょうか。これまで一般的だったDRAMなどと比較しても、数倍から十数倍程度の容量や通信速度を誇るメモリです。今回はそんなHBMについて、具体的な構造や世代毎の特徴、製造技術などを分かりやすく解説します。
HBMとは広帯域幅を持つDRAMのこと

HBM(High Bandwidth Memory)とは、半導体技術の標準化団体であるJEDECによって規格化された、高い帯域幅を持ったDRAMのことです。一般的にメモリとCPU間でやり取りするデータ容量を大きくするには、データの転送速度を速くするか、帯域幅を広げることが有効です。しかしデータの転送速度を速めると消費電力や発熱量も増えてしまうという難点があるため、HBMでは一度にやり取りできるデータ容量を左右する帯域幅を広げることで、大容量のデータを高速でやり取りできるようにしました。
DRAMとは?
そもそもDRAMとは、対になったトランジスタとコンデンサを利用する揮発性メモリのことで、コンデンサに電荷を蓄えることでデータを保持します。時間が経つと電荷が揮発してデータが失われるため、定期的にデータを書き直すリフレッシュ操作が必要な様子から、動的メモリとも呼ばれます。なおDRAMと対をなすRAMとして、リフレッシュ操作が不要なSRAMというメモリもあるので、興味のある人は併せて覚えておくと良いでしょう。
HBMの構造
HBMはシリコンインターポーザと呼ばれるベース部品の上に、メインの演算部であるロジックシリコンダイを載せ、更にその上にメモリの役目を果たすDRAMシリコンダイを複数枚積層した3次元構造になっています。それぞれのシリコンダイ同士は、TSV技術によって作られた貫通電極によって電気的に接続されています。なお、上記の構造ではDRAMシリコンダイが発する熱をロジックシリコンダイを経由して排熱することになるため、これらを分けて配置する2.5D実装を行っているメーカーもあります。
HBMが使用される分野や機器
HBMは従来のメモリと比較して大容量かつ高速でデータ通信が行えるため、気象予測などの複雑な物理計算を行うスーパーコンピュータや、膨大なデータを用いて機械学習を行う人工知能など、最先端の高性能アプリケーション機器に使用されることが多いです。また高画質の映像をリアルタイムでレンダリングするゲームや映画などにおいて、最も負荷が掛かるGPUに使用されることもあります。
HBMの世代の違い
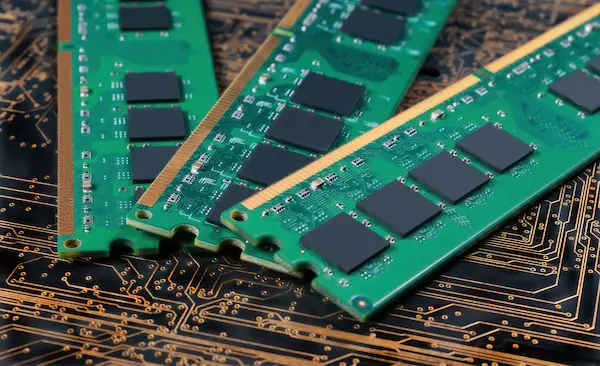
HBMの具体的な仕様は世代によって異なり、JEDECが公開している仕様書に記載されております。仕様の違いなどにも触れながら、それぞれの世代について解説していきましょう。
第一世代となるHBM1
初めて発売された第一世代のHBM1は、帯域幅が128GB/sで積層可能なDRAMシリコンダイは4層までという仕様でした。またシリコンダイ1枚あたりのメモリ容量は2Gbits(≒256MB)のため、ダイを4層重ねることで1GBのメモリ容量となります。同時期に使用されていたDDR4の帯域幅が25.6GB/s程度であったことを考えれば、HBMが如何に高速かつ大容量なデータのやり取りができるかが分かるでしょう。
第二世代のHBM2と強化版のHBM2E
HBM1に続く第二世代として登場したのがHBM2で、帯域幅は256GB/s、DRAMシリコンダイの積層数は最大8枚へと強化されました。またシリコンダイ1枚あたりのメモリ容量も8Gbitsとなったことで、総合的なメモリ容量も最大8GBとなっています。
そしてHBM2の強化版として登場したのがHBM2Eです。積層可能なシリコンダイの枚数は8枚のままですが、1枚あたりのメモリ容量が16Gbitsとなったことで、総メモリ容量が16GBへと強化されました。また帯域幅も460GB/sの物が登場し、HBM2と比較しても倍近い性能となりました。
HBM3と後継世代のHBM3E、HBM4
続くHBM3ではシリコンダイの積層枚数が12枚へと進化し、1枚あたりのメモリ容量は最大で32Gbits、帯域幅も最大819GB/sへと大きく進化しました。将来的には積層枚数は16枚まで対応するとも発表されていることから、デバイス1つあたりのメモリ容量は最大64GBにもなります。メーカーによってはHBM3の強化版となるHBM3Eについてもリリースしており、更に最新の世代となるHBM4についても暫定的な仕様がJEDECより公開されていることから、今後も新たな世代のHBMが出る可能性は高いでしょう。
HBMに欠かせない2つの技術

高い帯域幅を持ったHBMを製造する上では、精密な積層技術とTSV技術の2種類が重要となります。それぞれの技術の概要について解説していきましょう。
精密な積層技術
非常に薄く作られたシリコンダイは僅かな要因で反りや曲がりが発生する可能性があり、ベースのインターポーザ面積が大きくなる2.5D実装では特に発生しやすくなります。そのためHBMの製造では、シリコンダイやインターポーザの厚みや材料を工夫した上で、応力などを監視しながら精密に積層する技術が求められます。
またシリコンダイ同士を電気的に接続するはんだの部分をマイクロバンプと呼びますが、配線バスの高密度化にはバンプ径やバンプ同士の間隔を極力小さくすることも重要となります。特に僅かな厚みの違いや位置のズレが生じると、シリコンダイ同士が電気的に接続されない可能性もあることから、マイクロバンプの印字にも高い技術が求められるのです。
TSV技術
TSV(Through silicon via)技術とは、シリコン基板に微細な穴(ビア)を開けて金属を流し込むことで、基板を垂直に貫く貫通電極を作り出す技術のことです。TSV技術を用いることでチップと基板の間の配線距離が大幅に短縮でき、従来の方式よりも遅延や消費電力が少ない通信が可能となります。また貫通電極を使用すればチップと基板を接続する部分にボンディングワイヤも不要になるため、チップの搭載に必要な面積を極限まで減らすこともできます。
HBMはコスト面に課題が残る
非常に優れた特徴を持つHBMですが、複雑で精密な技術が要求されるため、製造コストが高いのが課題とされています。特に世代を追うごとにシリコンダイの積層枚数が増加傾向にあり、要求される技術も日に日に高くなっていくことが予想されるため、当面は高性能なアプリケーション以外に使用されることは少ないでしょう。一方で半導体製造分野における技術は日進月歩で進歩しているのも事実であり、将来的には製造コストが大幅に安くなることにも期待が持てます。
まとめ
今回は最先端の高性能メモリとして知られるHBMについて、構造や世代毎の特徴などを網羅的に解説してきました。まだまだ汎用的な機器に搭載されることは少ないですが、最先端の分野において非常に重要な役割を果たすメモリであるため、今後もその進歩に期待しておきましょう。
当サイトFREE AIDは、機電系を始めとしたエンジニアのフリーランス専門求人を扱っています。
→機電系フリーランスエンジニア求人はこちら
また、フリーランスエンジニアとして働きたい方に合った案件探しや専門アドバイザーの活動サポートも無料で行っています。
→フリーランス無料支援に興味がある方はこちら

この記事の運営元:株式会社アイズ
「アウトソーシング」「ビジネスソリューション」「エンジニアリング」「ファクトリーオートメーション」の4つの事業を柱に、製造業やICT分野の課題解決を力強くサポートします。
フリーランスの機電系エンジニア求人情報サイト「FREE AID」を運営しています。
 機電系求人はこちら
機電系求人はこちら
設計技術者(樹脂、金属部品)
- 単価
40~50万円
- 職種
- 機械設計
- 詳細を見る
FPGAの設計開発:電気電子設計
- 単価
70~80万円
- 職種
- 電気電子設計
- スキル
- ・FPGA論理設計、RTLコーディング、論理検証環境構築、論理検証・RTLコード:VHDL・論理検証ツール:Siemens製Questa/ModelSIM
- 地域
- 東京
- ポイント
- #高単価
- 詳細を見る
UI画面の設計業務:電気電子設計
- 単価
64〜万円
- 職種
- 開発
- 電気電子設計
- スキル
- 必要スキル: ・電源回路は複数回経験し、設計動作確認など、一人でもある程度やるべきことが分かる。 ・数十頁のデータシートを読み、要求仕様(タイミング/電圧など)が理解できる ・その他左記の回路の種類の中で、回路設計の実務経験が1回以上ある。 ・回路修正ができる(半田付け、ジャンパー処理)
- 地域
- 関西
- ポイント
- #業務委託#駅近
- 詳細を見る
【急募】工作機械メーカーにおける自社製品の制御設計
- 単価
40~50万円
- 職種
- 電気電子設計
- スキル
- 基本的なPCスキル産業用機械・装置の電気設計経験
- 地域
- 山梨県
- ポイント
- #業務委託
- 詳細を見る





