トンネルFETの原理や構造とは?MOSFETやCMOSも解説!
2025年5月10日更新
この記事を書いた人

大手メーカー「コマツ」、「オムロン」などで7年間、アナログ回路エンジニアとして設計・評価業務に従事。
ECU、PLCなどのエレキ開発経験を多数持つほか、機械商社での就労経験も有する。
株式会社アイズ運営の機電系フリーランスエンジニア求人情報「FREEAID」専属ライターとして、
機電分野の知識と実務経験を活かし、専門性の高い記事執筆を行っている。
MOSFETやCMOSなどに類似するトランジスタデバイスとして、トンネルFETを聞いたことはあるでしょうか。今回は従来のFETより消費電力面で優れるトンネルFETについて、具体的な特徴やメリット、課題など基本的な内容を解説します。付随する知識として、MOSFETやCMOSについても解説していくので、ぜひ最後まで読んでみてください。
トンネルFETの構造や原理とは?
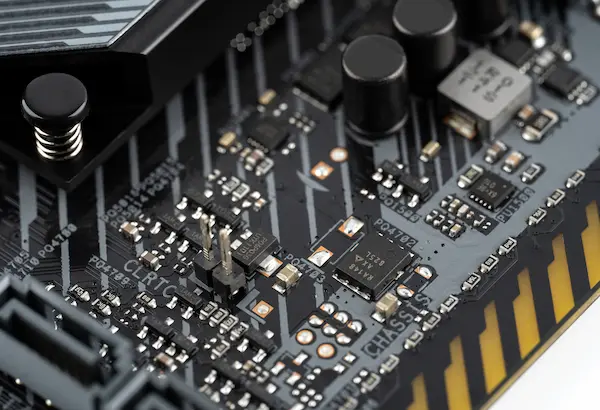
トンネルFETは、日本語で「トンネル電界効果トランジスタ」と訳されるデバイスのことです。MOSFETに似た構造をしているものの、ドレインとソースにおける半導体の型が逆になっているのが特徴で、ドレインがp型半導体であればソースはn型半導体となります。
スイッチング動作に量子力学における「トンネル効果」を利用しており、ゲート電圧を変えてポテンシャル障壁を変調することで、ドレインに流れる電流を制御しています。現時点ではまだ実験段階にあるものの、従来のMOSFETやCMOSを大きく上回る省電力性能を持っていることから、次世代デバイスへの搭載が期待されている素子です。
量子力学におけるトンネル効果とは
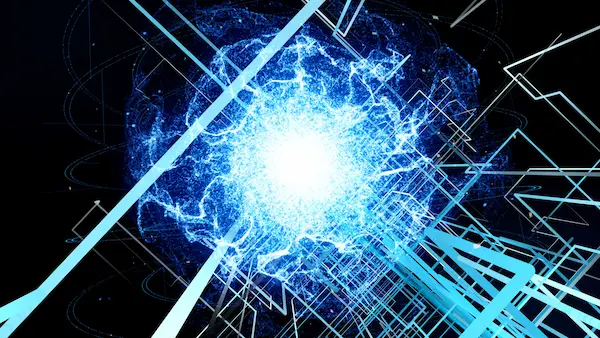
トンネルFETの技術的な核となるトンネル効果についても触れておきましょう。トンネル効果とは、微小領域において、粒子が本来超えられない障壁を一定確率で超えてしまう現象のことです。電子や原子など、非常に小さなスケールの物理現象について研究する学問を量子力学と呼びます。量子力学の世界では我々の直感に反する物理現象が発生し、粒子の位置と運動量は確定できないとする不確定性原理もその1つです。
不確定性原理によると、電子の存在は空間的な広がりを持つ確率の雲によって表され、近傍にポテンシャル障壁があってもその向こう側にまで広がりを持つとされています。そしてポテンシャル障壁の厚みによっては電子がポテンシャル障壁をすり抜けることがあり、これをトンネル効果と呼びます。トンネル効果はトンネルFETだけでなく、量子コンピュータや走査型電子顕微鏡などにも応用される現象です。
トンネルFETと類似するMOSFET・CMOSとは
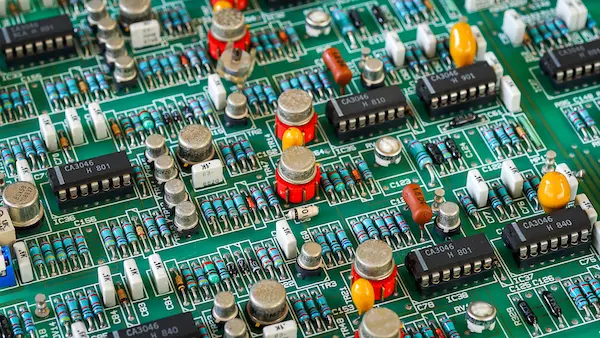
トンネルFETの性能を理解する上では、類似する電子部品であるMOSFETやCMOSについても理解しておく必要があります。これらの製品についても概要を紹介します。
MOSFETとは
MOSFETはゲート、ソース、ドレインの三つの電極を持つトランジスタデバイスの一種で、日本語では金属酸化膜半導体電界効果トランジスタと訳されます。ゲートとソース間に電圧を印加するとゲート付近に反転層が形成され、ドレインとソース間の抵抗値が下がって導通することから、スイッチングデバイスとして使用されることが多いです。
MOSFETは大きくpチャネル型とnチャネル型の2種類に大別され、pチャネル型であればn型半導体のボディにドレインとソースがp型半導体となった構造をしています(nチャネル型であれば逆の構造となる)。従来のバイポーラトランジスタが電流駆動であったのに対し、MOSFETは電圧駆動であるため、消費電力が少ないのが特徴です。
CMOSとは
CMOSとは、pチャネル型MOSFETとnチャネル型MOSFETを組み合わせ、それぞれが相補的に動作するよう構成したデバイスのことです。MOSFETと同様に消費電力が少ないのが特徴で、入力電圧によってpチャネル型とnチャネル型のどちらか一方が必ずオフになるため、MOSFET2個分の電力を消費することもありません。さらに従来のバイポーラトランジスタに比べて高速な動作も可能であるため、多くのLSIで使用される主要素子として知られています。
トンネルFETはMOSFETより消費電力が少ないのがメリット
トンネルFETの最大のメリットといえば、消費電力の低さが挙げられます。MOSFETなどのトランジスタデバイスにおいて、電流を1桁分変化させるために必要な電圧の変化量をS値と呼びます。S値が小さいほど急峻なターンオン特性が得られ、駆動電圧や待機時に流れるオフ電流が少なく済むため、デバイスで消費する電力も抑えられます。
従来のMOSFETでは60mV/decade程度がS値の限界と言われており、電圧でいえば0.5V以上の駆動電圧が必要とされていました。一方のトンネルFETでは、60mV/decadeを下回るS値が実現可能であり、駆動電圧も0.3V程度のものが開発されていることから、従来のCMOSとは比べ物にならないほど少ない消費電力を実現できるのです。
トンネルFETの課題と現状
トンネルFETはMOSFETに比べてオン電流が低いのが課題と言われています。前提として、トランジスタデバイスでは、ゲート容量を素早く充電するために一定以上のオン電流を流す必要があります。トンネルFETでは駆動電圧を上げることでオン電流を大きくできるものの、MOSFETを下回る駆動電圧で動作できるのがトンネルFETの強みであるため、駆動電圧を上げる行為はトンネルFETの強みを失うことになりかねません。そのため現状としては、低いS値と高いオン電流の両方を実現できるトンネルFETの開発が待たれている一方で、高いオン電流が不要なデバイスへの限定的な利用を模索している状況です。
トンネルFETの採用が期待されるデバイス
続いてトンネルFETの採用が期待されている具体的な用途について解説していきます。トンネルFET自体はまだ開発段階ではあるものの、製品化すれば今後のデジタル社会を大きく変えるデバイスであることを理解しておきましょう。
低消費電力が求められるセンサデバイス
全ての物がインターネットに接続されるIoT社会では、扱えるデータの総量を増やすため、膨大な量のセンサデバイスが必要になります。一方で、センサデバイスの増加は社会全体の消費電力の増加にも繋がるため、個々のセンサデバイスの消費電力がボトルネックとなり、電力の需給バランス調整が困難になるリスクが考えられます。
またセンサデバイスの寿命によっては、機器の交換やメンテナンスが頻繁に発生するため、莫大なランニングコストが掛かる可能性も無視できません。そこで、消費電力が少なく電気的ストレスも少ないトンネルFETを末端のセンサデバイスに採用することで、IoT社会における消費電力を抑えつつ、各種センサデバイスを半永久的に使用する未来に期待が持たれているのです。
中央制御デバイスや量子コンピュータなどへの利用
消費電力が少ないトンネルFETは、制御動作に伴う発熱量も少ないため、量子コンピュータやデータセンターにおける中央制御デバイスなどにも利用されることでしょう。背景として、量子コンピュータなどの超高性能なコンピュータでは演算に伴う発熱量が大きくなりがちで、CMOSが発する熱がボトルネックとなり、コンピュータの性能を活かしきれない可能性が懸念されています。
またスマートフォンなどの普及により、中央制御デバイスに求められる処理能力も向上し続けており、同じく発熱量の低減が急務となっています。これらのデバイスにトンネルFETを採用できれば、素子の発熱量を気にせずに制御機器の性能を発揮できるのはもちろんのこと、これまで冷却機構に使っていた電力や面積を他の用途へ使うことで、さらなる高性能化が期待されています。
まとめ
今回は低消費電力化が実現可能なトンネルFETについて、基本的な構造や原理、メリット、課題などを網羅的に解説してきました。優れたS値が実現できるもののCMOSに比べてオン電流が低く、現時点ではまだまだ発展途上であることが理解できたのではないでしょうか。IoT社会の実現に向けて注目が集まる素子でもあるため、気になる方は今後の動向にも注目してみては如何でしょうか。
当サイトFREE AIDは、機電系を始めとしたエンジニアのフリーランス専門求人を扱っています。
→機電系フリーランスエンジニア求人はこちら
また、フリーランスエンジニアとして働きたい方に合った案件探しや専門アドバイザーの活動サポートも無料で行っています。
→フリーランス無料支援に興味がある方はこちら

この記事の運営元:株式会社アイズ
「アウトソーシング」「ビジネスソリューション」「エンジニアリング」「ファクトリーオートメーション」の4つの事業を柱に、製造業やICT分野の課題解決を力強くサポートします。
フリーランスの機電系エンジニア求人情報サイト「FREE AID」を運営しています。
 機電系求人はこちら
機電系求人はこちら
設計技術者(樹脂、金属部品)
- 単価
40~50万円
- 職種
- 機械設計
- 詳細を見る
FPGAの設計開発:電気電子設計
- 単価
70~80万円
- 職種
- 電気電子設計
- スキル
- ・FPGA論理設計、RTLコーディング、論理検証環境構築、論理検証・RTLコード:VHDL・論理検証ツール:Siemens製Questa/ModelSIM
- 地域
- 東京
- ポイント
- #高単価
- 詳細を見る
UI画面の設計業務:電気電子設計
- 単価
64〜万円
- 職種
- 開発
- 電気電子設計
- スキル
- 必要スキル: ・電源回路は複数回経験し、設計動作確認など、一人でもある程度やるべきことが分かる。 ・数十頁のデータシートを読み、要求仕様(タイミング/電圧など)が理解できる ・その他左記の回路の種類の中で、回路設計の実務経験が1回以上ある。 ・回路修正ができる(半田付け、ジャンパー処理)
- 地域
- 関西
- ポイント
- #業務委託#駅近
- 詳細を見る
【急募】工作機械メーカーにおける自社製品の制御設計
- 単価
40~50万円
- 職種
- 電気電子設計
- スキル
- 基本的なPCスキル産業用機械・装置の電気設計経験
- 地域
- 山梨県
- ポイント
- #業務委託
- 詳細を見る





